
競書31号
書道博物館と中村不折コレクションについて(二十九)

競書31号
現在、書道博物館では「センジモンって、なぁに?」を開催中です。千字文とは、一文字も重複のない一〇〇〇字を四字一句とした、都合二五〇句の韻文をいいます。今回展示されている作品の中に、智永の『真草千字文』(明拓)がありますが、これも不折コレクションの優品の一つです。真草千字文は、楷書(真)と草書(草)で書写したものです。楷書は当時「真書」と呼ばれていたために「真」の字が使われています。この作品を書いた智永は、王羲之の七代目子孫にあたり、生卒はあきらかではありませんが、陳から隋にかけて能書家として謳われ、特に草書、章草の名手として知られています。名を法極、俗姓を王氏といい、会稽(現在の浙江省紹興)の人です。兄の孝賓とともに仏道修行に入って永欣寺の僧となり、永禅師と称されました。
(書道博物館主任研究員 鍋島稲子(なべしま・とうこ)
![]()
競書30号
前回、このコーナーへ拙稿を提出したのが三月十日でした。まさかその翌日に日本がこのような事態になろうとは…。被害を受けられた地域の皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興を心よりお祈りいたします。
(書道博物館主任研究員 鍋島稲子(なべしま・とうこ)
![]()
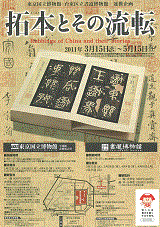 書道博物館と中村不折コレクションについて(二十七)
書道博物館と中村不折コレクションについて(二十七)
精錬誌29号
台東区立書道博物館と東京国立博物館は、同一テーマの展覧会を二館で同時期に開催する連携企画を実施してきました。この企画は台東区における文化振興を促進するのみならず、国内各地からの来館者も多く、近年の恒例事業となっています。
(書道博物館主任研究員 鍋島稲子(なべしま・とうこ)
![]()
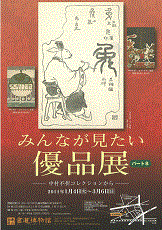 書道博物館と中村不折コレクションについて(二十六)
書道博物館と中村不折コレクションについて(二十六)
精錬誌28号
あけましておめでとうございます。本年も書道博物館は、充実した展示でがんばります。どうぞよろしくお願いいたします。
不折コレクションは、そのほとんどが中国関係の資料ですが、日本の書として奈良・平安の古写経や古文書、江戸の唐様書や明治の文豪たちの手紙などがあります。その中から今回は、空海の筆といわれる『心経』、藤原定信の『戸隠切』、良寛の『書巻』、幕末の三筆である巻菱湖の美しい楷書や、貫名菘翁の迫力ある行書を展示しています。水戸黄門で知られる徳川光圀や、幕末の大老井伊直弼の力強い書も見どころです。
中村不折記念室では、『坂の上の雲』の放映に伴い、正岡子規の『ホトトギス』に関する資料や、子規が制作した俳句カルタ、新春にふさわしい不折の書画作品を展示中。不折の眼を通してみた日本の文化を、じっくりとご堪能ください。
年末のドラマ『坂の上の雲』では、「子規、逝く」が放映されました。明治35年9月19日、朝から体調の良くなかった子規は、その夜に息を引き取ります。36歳という若さでした。書道博物館の斜向かいにある子規庵には、連日多くの人が見学にいらしています。
子規と不折との交友関係は、短い期間でしたが、大変深いものでした。雑誌『ホトトギス』の表紙を、子規の指示のもとに不折が作成していく過程からも、その一端を垣間見ることができます。
新春は、子規庵と書道博物館で、『坂の上の雲』の追体験をしてみるのもいいかもしれません。
(書道博物館主任研究員 鍋島稲子(なべしま・とうこ)
![]()
 書道博物館と中村不折コレクションについて(二十五)
書道博物館と中村不折コレクションについて(二十五)
精錬誌27号
現在、書道博物館では「不折コレクション、ベストセレクション。」という、開館十周年特集を開催中です。ベストセレクションが数多くあるので、期間を三期分けて展示しています。今回は、第三期に展示される名品を紹介しましょう。北宋時代の四大家として知られる、蔡襄(1012~1067)の『謝賜御書詩表巻』(皇祐5年・1053)、これは蔡襄の楷書の傑作として世に知られています。北宋の仁宗皇帝が、蔡襄に「君謨」という字を御書した一軸を賜り、それに感激した蔡襄が、その君恩に感謝すべく上表文と七言古詩一首を皇帝に奉ったものです。上奏文という性格上、書かれた文字も一貫して揺るぎなく、見事な筆さばきで書かれています。本文は37行で、巻末には北宋の米芾を筆頭に、鮮于枢、呉寛、陳継儒、董其昌など、元明清時代の錚々たる18家の跋が連なっています。また、跋に続いて犬養毅や呉昌碩、羅振玉などの観記もあります。
北宋内府の後、民間に流れ、清朝において再び内府の所蔵となりました。清朝末期には金石学者で知られる端方の所蔵となり、端方没後の1911年以降に遺族が整理し、日本に渡ってきました。そして1919年6月7日、文求堂を介して中村不折の有に帰しました。
2006年に東京国立博物館で開催された『書の至宝』展、その巡回展として上海博物館で開かれた『中日古代書法珍品』展において展示された際にも、大変話題となった作品です。
(書道博物館主任研究員 鍋島稲子(なべしま・とうこ)
![]()
その中で、今回展示される珠玉のコレクションを紹介しましょう。
王献之は、書聖といわれる王羲之の第七子であり、書は幼いころより王羲之に見込まれていました。王献之幼少の頃のこんなエピソードがあります。王献之が手習いをしていた時、その背後から王羲之がそっと筆を抜き取ろうとしましたが、しっかりと握られていて取ることができませんでした。この子は書において将来必ずや世に名をなすことができると王羲之が確信したといいます。実際、王献之は父王羲之と優劣つけがたいほどの名作を残し、特に行書や草書においてはその艶かしい美しさには、王羲之以上と評価されるものもありました。
当館所蔵の王献之『地黄湯帖』は、北宋時代に皇帝のコレクションとして内府に珍蔵されていました。南宋時代の高宗による外題簽も付されています。その後、南宋の大収蔵家として知られる賈似道の手に渡り、明時代に入ってからは文徴明、王寵、文彭が所蔵、清時代では孫星衍、呉栄光、羅振玉所蔵の後、明治44年12月3日、文求堂を介して中村不折の有に帰しました。巻末に文彭、常生、成親王、英和ら六家の観記や跋があります。
この作品の他にも、中村不折が苦心して蒐集した、中国書道史を彩る名品の数々が展示されますので、どうぞたっぷりとご覧ください。
(書道博物館主任研究員 鍋島稲子(なべしま・とうこ)
![]()
今夏は、上野の山とその麓で、中国古代文字の展示が流行りです。東京国立博物館では、現在開催中の特別展『誕生!中国文明』で古代文字資料を紹介していますし、当館でも同様に『漢字のはじまり-古代文字の不思議をさぐる-』と題して、古代文字の特集展示を行なっています。
占いに用いた最古の漢字である甲骨文にはじまり、王室の権威を誇示した青銅器の銘文、そして春秋戦国時代の動乱期を経て、秦の始皇帝が文字を統一して制定した正式な篆書まで、古代文字はさまざまに変化を遂げていきました。
古代文字の不思議なかたちを通じて、限りないひろがりを持った漢字の世界をたっぷりとお楽しみください。
(書道博物館主任研究員 鍋島稲子(なべしま・とうこ)
![]()
精練24号(2010.6.7月号)
中村不折コレクションには、拓本の類が数多くありますが、今回の展覧会では、墓誌銘の拓本と、その原石を紹介いたします。現代の日本における墓誌は、墓石とは別に戒名や生没年などを刻し、墓所に建てる石碑を指します。中国に起源を持つ本来の墓誌は、姓名や生没年月日のほか、墓主の地位や功績を石などに刻し、棺とともに墓中に埋葬しました。こうした墓誌の風習は日本にも伝来しましたが長くは続かず、7世紀の後半頃から行われ、8世紀の終わりには姿を消してしまいました。
中国では、後漢時代(1~2世紀)以来、地上に立派な墓碑を建てる風習がありました。しかし、三国時代の魏(3世紀)の曹操や、西晋時代(3~4世紀)の武帝は、厚葬(贅沢な葬儀)は虚栄心を増長させるだけで、財産を失い人々に害を及ぼし、ひいては国力が衰退するとの理由から、建碑を禁止しました。そこで、墓碑を小型化して墓中に埋める形式が徐々に浸透し、他の副葬品との関係から、墓誌は正方形の石に統一されます。やがて、蓋の役割をする蓋石と、銘文を刻した誌石とを上下一組とする形が墓誌の基本様式となります。南北朝時代(5~6世紀)には、この墓誌のスタイルが確立し、以後長く受け継がれてきました。
長い間地中にあった墓誌は、風雨によって碑面が傷むこともなく、保存状態が良好で、刻された文字も鮮明に残っています。また、ほとんどの墓誌銘に年号が記されているため、書写年代が確定でき、時代ごとの書風の変遷をたどることができます。中国書法史において、墓誌銘はその時代の書風や文字の特徴をつぶさに観察できる格好の資料として、また、正史の欠を補う文献資料として、大変重要です。
墓誌銘は、多くが楷書であり、時代によってさまざまな楷書の美しさが表現されています。最も多く制作された北魏時代の墓誌銘は、粗削りながらも、鋭さと力強さを兼ね備えた勢いのある楷書で書かれていますし、隋時代の墓誌銘は、南朝の優雅さと北朝の素朴さとが融合した安定感のある楷書、唐時代には、完成された整斉な楷書の字姿がうつしだされています。また南北朝時代、南朝には墓誌の例がほとんどありませんが、隷書と楷書の要素が入り混じった自由な雰囲気の『劉懐民墓誌銘』は、南朝の宋時代の数少ない貴重な遺例で、表情豊かな書風を伝えています。
今回の展示では、初公開15点を含む南北朝~唐時代までの墓誌銘拓本と、現存するわが国最古の墓誌『船氏王後墓誌銘』(原品は三井記念美術館蔵、国宝)の拓本、あわせて34点を一挙公開いたします。また当館では、南北朝時代の代表的な墓誌である四司馬墓誌の一つ『司馬昇墓誌』をはじめ、墓誌の原石を11点展示しています。墓誌銘の拓本だけでなく、国内では見ることが難しい貴重な墓誌の実物を、この機会に是非ご覧ください。
厚葬の禁止からうまれた墓誌。それは決して華美なものではありませんが、敬虔な想いを込めて刻まれた墓誌銘は、人々を圧倒する力強さと、見る者の心を癒す美しさを兼ね備えています。秘められたパワーを持つ墓誌銘の魅力を、どうぞたっぷりとご堪能ください。
書道博物館主任研究員 鍋島稲子(なべしま・とうこ)
![]()
 書道博物館と中村不折コレクションについて(二十一)
書道博物館と中村不折コレクションについて(二十一)
精練23号(2010.4.5月号)
昨今は、テレビドラマなどの影響もあり、幕末から明治にかけての動乱期がクローズアップされていますが、まさにその時期に生まれ育ったのが、今回展示の主役・中村不折です。
幕末の慶応二年、江戸に生まれた中村不折は、明治時代とともに歩みながら、画家・書家・収集家としての確固たる地位を築き上げました。今回の展示では明治期における不折の軌跡と、不折とつながりの深かった明治の文豪たちとの交流をたどります。
昨年末からのドラマ化もあってか、小説『坂の上の雲』があらためて脚光を浴びています。そこで描かれる正岡子規、夏目漱石、森?外らの生き生きとした姿は読む者に強い印象を与えます。彼らはみな、明治文学界の中心的な役割を担っていくことになりますが、彼らに少なからぬ影響を与えたのが、書・画の両分野を得意とした中村不折でした。
ジャーナリストでもあった正岡子規は、明治二七年、自らが編集に携わっていた新聞『小日本』に、不折を新聞挿絵の担当として起用しました。この時から不折は、『日本』、『朝日新聞』と所属は変わりますが、実に三十年にわたって新聞に「コマ絵」(記事とは独立した絵画)を描きつづけたのです。子規とともに日清戦争へ従軍した際に目にした清国の光景、パリ留学時代のヨーロッパ通信、日本各地の名所旧跡を訪ねる連載旅行記、毎年正月恒例の十二支シリーズなど、コマ絵の題材の幅広さと斬新な意匠は、多くの読者を獲得しました。
やがて、その絵の持つ独特の視点と構図が評判となり、不折のもとには本や雑誌の装幀や挿絵の依頼がくるようになります。例えば夏目漱石の『吾輩は猫である』、島崎藤村の『若菜集』、伊藤左千夫の『野菊の墓』、雑誌では正岡子規編集の『ホトトギス』、森?外編集の『めさまし草』など、明治文学を代表する作品が不折の装幀や挿絵で彩られました。?外にいたっては、遺言書に「…墓ハ森林太郎墓ノ外一字モホル可ラズ。書ハ中村不折ニ依頼シ…」と、自らの墓の文字までも不折を指名しています。不折の書と画がいかに当時の文人たちに愛されていたかがわかります。
こうした明治の文豪たちとの交流は、不折にとってもかけがえのないものでした。彼らからの手紙は、軸装や巻子に仕立てられ、不折自筆の題簽が貼られて大切に保存されてきました。日常のたわいないやりとりが深く刻み込まれた友人たちの肉筆こそが、不折にとっての「明治の書」そのものであったのでしょう。
日本があらたな国のかたちを模索しつつ揺れていた明治という時代を、中村不折の手がけたブックアートや挿絵、そして不折愛蔵の文豪の書から感じとっていただければ幸いです。
書道博物館主任研究員 鍋島稲子(なべしま・とうこ)
![]()
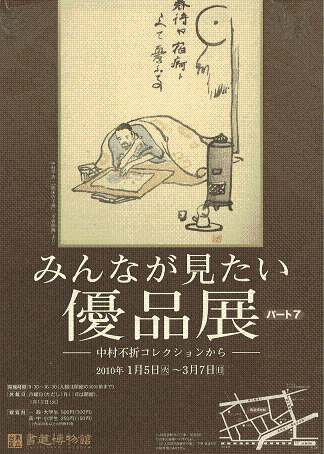 書道博物館と中村不折コレクションについて(二十)
書道博物館と中村不折コレクションについて(二十)
精練22号(2010.2.3月号)
明けましておめでとうございます。今年も書道博物館は、時代の波に乗りながら、みなさんが楽しめる展示を心がけていきたいと思います。
新春恒例企画『みんなが見たい優品展 パート7-中村不折コレクションから-』では、当館に設置している「展示希望ノート」に書かれた作品を、年に一度ご要望にお応えできる範囲で展示しています。
今回は、甲骨文から楷書まで、各書体の代表的な作品が選ばれています。最古の漢字といわれる殷時代の甲骨文では、書風変遷の第1期(紀元前13世紀)に相当する牛肩甲骨とその拓本、金文では、西周時代後期(紀元前8世紀)の青銅器「史頌●(皀+殳)」とその拓本、そして篆書の源流といわれる大篆では、戦国時代の「石鼓文」(紀元前5~4世紀)、秦の始皇帝が大篆を基礎に文字統一を行った際、正式な篆書として確立した小篆は「泰山刻石」(紀元前219)、隷書は、後漢時代後期の流麗で華やかな「曹全碑」(185)が並びます。
また行書や草書では、東晋時代の王羲之(303?~361?)による「蘭亭序」や「十七帖」、楷書では、北魏時代の「牛?造像記」(495)や、隋時代の「美人董氏墓誌銘」(597)、そして初唐の三大家、虞世南の「孔子廟堂碑」(626)、欧陽詢の「九成宮醴泉銘」(632)、?遂良の「雁塔聖教序」(653)など、書を学ぶ上では欠かすことのできない主要な古典が勢ぞろいします。時代順に見れば、書体の歴史も同時に追うことができます。
上記の他に、中村不折記念室では、新春にふさわしい不折の書画作品、カルタなども展示しています。また、『坂の上の雲』放映に伴い、正岡子規筆の手紙やカルタ、不折が描いた子規像なども紹介しています。
近年、テレビや漫画において、書をテーマにしたストーリーが取り上げられています。携帯電話が筆に変形する“ショドウフォン”で宙に文字を書き、書かれた文字の「モヂカラ」を操って変身するという『シンケンジャー』を見ている子どもは、「ショドウ」は筆で書くということを知っています。また、弱小の高校書道部が書の古典を学びながら成長していくという『とめはねっ!』を読んでいる学生は、書の名品を自ずと鑑賞しています。今回の展示では、『とめはねっ!』に出てくる拓本も紹介しています(2010年1月よりドラマ放映)。
書に親しみを持つことができるこうした機会を通じ、当館ではより多くの人たちに書を楽しんでもらいたいと思っています。教科書、漫画やドラマにも登場する書の名品を、中村不折コレクションでぜひご堪能ください。
書道博物館主任研究員 鍋島稲子(なべしま・とうこ)
![]()
 書道博物館と中村不折コレクションについて(十九)
書道博物館と中村不折コレクションについて(十九)
精練21号(2009.12 2010.1)
書道博物館では、秋の企画展として顔真卿特集が開催されています。本連載の中村不折コレクション(二)でも触れましたが、今回、後期のみの特別公開となる顔真卿の「自書告身帖」について、少し見てみましょう。
「自書告身帖」の「告身」とは辞令の意であり、これは顔真卿が吏部尚書(人事担当)から太子少師(皇太子の教育係)に転任するよう命じられた時の辞令を、顔真卿自らが書したものです。顔真卿七十二歳の折の建中元年(七八〇)に書かれたものであるため、「建中告身帖」ともいわれています。顔真卿の政治的な活躍ぶりは周知の通りですが、官界にあっては顔真卿の頑固な性格が災いし、宰相から反感を抱かれることが多かったようです。この辞令は、時の宰相であった楊炎から告げられた、いわば“降格人事”であり、要職から閑職へうつされた時のものです。顔真卿の剛直さは権臣との対立を生み、彼は度々こうした閑職に左遷されていますが、降格人事の辞令を自ら書くという、皮肉にも似たささやかな抵抗もまた、顔真卿の人間味が感じられて、非常に興味深い作品の一つといえます。
「自書告身帖」は、唐時代の肉筆であるということのみならず、歴代名家の跋文があることでも有名です。巻子を開くと、巻頭に乾隆帝の題識があり、前隔水には南宋時代の理宗皇帝の筆による「唐顔真卿之告」の題字、再び乾隆帝の七言絶句四首の題詩があります。そして顔真卿の告身が書かれ、その後には米友仁の鑑定跋、蔡襄の跋、董其昌の跋、徐守和の跋が続き、最後は丁振鐸・陸潤庠の観款で締めくくられています。
本作品は、乾隆帝時につくられた立派な紫檀の箱に収められています。箱の側面と蓋表面には雲竜文様が彫刻され、箱蓋表には玉に刻された「乾隆御賞 顔魯公自書告身神品」の文字がはめ込まれています。乾隆帝がどれほどこの作品を大切にしてきたか、その細やかな心遣いが伝わってきます。後期展示では、この紫檀の箱も同時公開いたします。
台東区立書道博物館主任研究員・鍋島稲子
精錬20号「2009年10,11月号]
今年は顔真卿の生誕1300年にあたります。顔真卿の作品蒐集にはことのほか情熱を傾けた中村不折のコレクションから、選りすぐりの名品をご紹介いたします。題して「中村不折コレクション・顔真卿特集」…タイトルもストレート勝負です。
顔(がん)氏は、代々訓詁(くんこ)と書法を家学とする名門の一族で、曽祖父の顔(がん)勤(きん)礼(れい)以来、能書家ぞろいで知られています。中でも顔(がん)真(しん)卿(けい)(709~785)は、唐時代を代表する書家です。字(あざな)を清(せい)臣(しん)といい、開元22年(734)、26歳で進士に及第、唐の玄宗(げんそう)・粛宗(しゅくそう)・代宗(だいそう)・徳宗(とくそう)に仕えました。天宝14年(755)に起きた安禄山(あんろくざん)の乱に際し、顔真卿は多くの肉親を失いながらも、義軍として抵抗し、唐王朝の危機を救いました。建中4年(783)、今度は李希烈(りきれつ)によって反乱が企てられたときにも顔真卿は敵地に赴きますが、捕らえられて蔡州(河南省)の龍興寺で殺害されるという悲壮な最期を遂げます。顔真卿77歳のことでした。後に忠臣烈士として尊ばれ、その書は今なお多くの人々に影響を与えつづけています。
顔真卿の作品は、歴代能書家の中でも多く残され、その書体もさまざまで、楷書、行書、草書のほか、楷書と隷書をまぜたもの、草書に篆書や隷書をまぜたものなど、混交体のような作品も書いています。顔真卿の本領は楷書にあったといわれ、多くの碑文を楷書で揮毫しています。その書風は一碑一面貌といわれるほど、石碑ごとに表情が異なり、顔真卿の楷書表現の幅の広さがうかがえます。
顔真卿の筆法は蚕頭(さんとう)燕尾(えんび)といわれ、蚕の頭のような丸い起筆と、燕の尾のように先端がわかれたはらいを特徴とします。当館では、楷書作品の肉筆における唯一の作例として名高い『自書告身帖』を所蔵しています。運筆の様子をつぶさに観察できる本作品は、顔真卿の書法を知る上でも大変貴重なものといえるでしょう。
この秋は、書道博物館で顔真卿の書業の数々をぜひご高覧ください。
台東区立書道博物館主任研究員・鍋島稲子
![]()

精錬19号「2009年8,9月号]
昨年のちょうどこの時期、清朝碑学派の足跡を辿る展覧会を紹介したことがあります。その時にも少し書きましたが、中村不折コレクションは、清朝碑学派の作品そのものよりも、碑学派が学んだ拓本やそれらに書かれた跋文など、彼らの学問的背景となった資料が充実していますので、昨夏はそれらを中心に展示しました。今年は、清朝碑学派の一人、書画篆刻の各分野に異彩を放った趙之(ちょうし)謙(けん)の生誕一八〇年にあたります。これを記念して、東京国立博物館と台東区立書道博物館の二館において、趙之謙の回顧展を開催することになりました。今回の展覧会は、不折コレクションのみならず、他の博物館・美術館や個人所蔵の趙之謙作品を紹介するというものです。清時代も十九世紀を迎え、学問の進展を背景に、新しい書風が生み出されようとする頃、その中心的な役割を果たした人物が、趙之謙(一八二九~八四)です。
趙之謙は、浙江省(せっこうしょう)紹(しょう)興(こう)の富裕な家に生まれましたが、少年の頃に家産が傾き、貧困を余儀なくされます。二二歳で浙江の按察使(あんさつし)(省の司法長官)であった繆(ぼく)梓(し)の幕客となり見識を広め、三一歳で郷(きょう)試(し)(科挙(かきょ)の一次試験)に及第しました。ところが、この頃から太平(たいへい)天国(てんごく)の乱は江南の地に及び、繆梓は戦死、趙之謙は紹興に非難するものの、妻は戦禍を被り死亡、紹興の自宅も焼失してしまいます。趙之謙三四歳のことです。
翌年、趙之謙は会(かい)試(し)(科挙の二次試験)を受験するため北京に赴き、そこで胡?(こじゅ)(一八二五~七二)・沈樹鏞(しんじゅよう)(一八三二~七三)・魏錫曾(ぎせきそう)(?~一八八一)ら同好の士を得て、当時脚光を浴びていた金石学(きんせきがく)に没頭します。しかし、再三にわたり挑戦した会試にはことごとく失敗、ついに高級官僚の途を断念します。
四四歳の時に江西省(こうせいしょう )に赴任、五年の歳月を費やし、地方史『江西通(こうせいつう)志(し)』を完成させます。その後は知(ち)県(けん)(県の行政長官)の地位に甘んじ、江西省各地の知県を歴任しますが、在職中に過労がたたり、五六歳で病没しました。
不遇な経歴と報われない深い学識は、趙之謙の豪邁(ごうまい)な性格と相まって、難解な詩文や鬱勃(うつぼつ)たる詩情をたたえた書画篆刻に昇華され、とりわけ書においては北魏時代の書に心酔し、「北魏書(ほくぎしょ)」という未曾有の表現を確立しました。中国古代の文字を学び、新しい境地を開いた碑学派は、趙之謙の出現によって全盛期を迎えたといっても過言ではありません。後世に大きな影響を与え、今なお多くの人々を魅了する趙之謙の作品をご高覧ください。
書道博物館主任研究員 鍋島稲子(なべしま・とうこ)
![]()
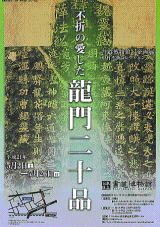 書道博物館と中村不折コレクションについて(十六)
書道博物館と中村不折コレクションについて(十六)
精錬18号「2009年6,7月号]
今回の展覧会では、不折コレクションから「龍門二十品」の拓本を紹介しています。「龍門二十品」とは、中国三大石窟の一つとして知られる龍門石窟内に刻された数ある造像記の中から、特に書法の優れている二十種を選んだものです。龍門石窟は、河南省洛陽から南へ十四キロ下った、伊水とよばれる川の両岸にあります。
龍門石窟の造営は、仏教の興隆と保護を目指すべく北魏時代の皇帝たちの発願によって国家事業として始められ、唐時代の中頃に至るまで続けられました。龍門石窟には大小合わせて二千以上の洞窟があり、これら洞窟内部の壁には、多くの仏像と、その造仏の由来や願文を記した造像記がすき間なくびっしりと刻されています。その中で最も早い時期に開鑿された古陽洞に「龍門二十品」の多くがあります。「龍門二十品」は、北魏時代の楷書の力強さを最大限に表現したものとしてよく知られており、書としての価値は非常に高いものがあります。また、書道博物館の創設者である中村不折が、書道研究を志す契機となった清国滞在に際して入手した拓本でもあり、その後の不折の理論と実践に大きな影響を与えました。したがって書道史上の価値はいうまでもありませんが、この「龍門二十品」は、同時に書道博物館コレクションの出発点として、また中村不折自身の書作品における原点としても大変意義ある資料といえます。
当時、不折が蒐集した「龍門二十品」の内容は、現在と若干異なることも興味深い点です。「龍門二十品」という呼称が広く知られるようになったのは、清末~民国時代の学者・康有為が著した書論『広芸舟双楫』(清・光緒十五年・一八八九)においてです。康有為の二十品には「優填王造像記」が入っており、不折コレクションの二十品も同一の内容になっています。不折は当時のベストセラーである『広芸舟双楫』を熟読し、最新の清朝書学を知りえる書物から、大きな影響を受けたであろうことは、大正三年(一九一四)に井土霊山とともに『広芸舟双楫』を翻訳し、『六朝書道論』として上梓していることからも窺われます。不折が『広芸舟双楫』の二十品目録に準じたのは、むしろ当然かもしれません。今日ではこれを二十品から省いて、かわりに「馬振拝造像記」を入れるのが一般的となっていますが、不折コレクションの「龍門二十品」は、「優填王造像記」を入れた康有為バージョンのままで伝わっています。
明治二八年(一八九五)に不折が清国へ渡った際、最初に出会った拓本が「龍門二十品」の拓本であり、その後、四年間のフランス留学時代に毎晩手習いしたのも「龍門二十品」の拓本でした。不折の愛した「龍門二十品」の野趣あふれる楷書の魅力を存分にご堪能ください。
書道博物館研究員 鍋島稲子(なべしま・とうこ)
![]()
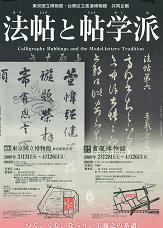 書道博物館と中村不折コレクションについて(十五)
書道博物館と中村不折コレクションについて(十五)
平成21年 4,5月号
現在、東京国立博物館と書道博物館において『法帖と帖学派~つぐ、くむ、ならう、王羲之の系譜~』を開催しています。両館それぞれの所蔵品を所蔵館にて展示し、観覧者のみなさんが両館を巡ることで、大展覧会の雰囲気を味わってもらおうというものです。両館が同一テーマを設けて開催する共同企画は、今回が六回目になります。法帖について少しお話しましょう。現在のような印刷技術のなかった古代の中国においては、早くから拓本の技法が考案され、学書や鑑賞に供されてきました。拓本の文化を背景に、名筆を選んで木や石に刻し、これを本仕立てにしたものを「法帖」といい、多くの人々の書を集めたものを「集帖」、一人の人物の書を集めたものを「専帖」、一つの作品のみを収録したものを「単帖」といいます。
北宋時代の淳化三年(九九二)、太宗皇帝は宮中の所蔵品から歴代の名筆を選出・編修した法帖を刊行させました。これが勅撰になる最古の集帖『淳化閣帖』です。王羲之・王献之の行草書や、その周辺の書を収めた『淳化閣帖』は、後世に大きな影響を与えました。明時代には著名な収蔵家が輩出し、収蔵品を誇示するかのように、家刻の法帖を刊行するようになり、その風潮は清時代に及びます。宋時代から元・明・清時代にわたって、王羲之・王献之をはじめとする歴代の名筆は、法帖によって代々受け継がれ、法帖は書を学ぶ者の基本テキストとして尊ばれてきました。中国書法史を彩る多くの書人は、法帖を介して古の精華を汲み取り、これを倣うことによって、自らの書風を創り上げてきたのです。
今回の展示では、官刻や家刻のさまざまな法帖と、法帖を学んで一家を成した「帖学派」とよばれる清時代の諸家の作例を紹介しています。これらを通じて、古人の古典に対する様々な想いを感じとっていただければ幸いです。
台東区立書道博物館研究員 鍋島稲子(なべしま・とうこ)
![]()
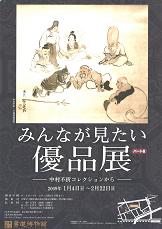 書道博物館と中村不折コレクションについて(十四)
書道博物館と中村不折コレクションについて(十四)現在書道博物館では、中村不折コレクションから宋・元時代の書画を展示しています。いわゆる肉筆の書画のみならず、拓本や写経類まで陳列しているのが大きな特徴です。書の世界では、宋時代の代表的な人物として北宋の四大家が知られていますが、彼らの肉筆作品は稀少であるため、今回の展示では拓本での作品も紹介し、四大家たちがどのような書風であったか、その違いについてもわかるようにしています。では、北宋の四大家たちについて、簡単に触れてみましょう。北宋時代の書は、前期と後期に分けることができます。宋の建国当初においては、宋王朝の文化政策として王羲之・王献之の書風を尊重する傾向にありました。その一つに、北宋の太宗皇帝の命によって編集された『淳化閣帖』の成立があげられます。これは、宮廷に収蔵される二王及び歴代名臣の書を、全十巻にまとめたものです。北宋後期になると、伝統的な書風にとらわれることなく、個人の精神性を重視し、自由奔放で躍動感あふれる書風が興こります。この時期を代表する人物が、宋の四大家といわれる蔡襄(1012~1067)、蘇軾(1036~1101)、黄庭堅(こうていけん)(1045~1105)、米フツ(1051~1107)です。蔡襄は、皇帝からの信頼が厚く、皇帝の文書の原稿を担当する翰林学士や、宋の財政を統括する要職などを歴任した。文学にも長じ、茶人としても知られたといいます。書は、王羲之から顔真卿、楊凝式など名家の書を習い、各書体に通じました。顔真卿の影響が色濃い「顔真卿自書告身帖跋」や「万安橋碑」、そして楷書の傑作である「謝賜御書詩表巻」が代表作として世に知られており、その全てが今回展示されています。蘇軾は、北宋の四大家としてのみならず、詩の世界でも唐宋八大家の一人に数えられ、さらに学問においては進士に及第した後、天子の指示で不定期に実施された「制科」という超難関の試験に合格するなど、当時のスター的存在でした。新法党の王安石のとの政争に破れたり、左遷を受けたりするなど、官僚としては不運に終わりましたが、流刑の身でありながらも、書では「黄州寒食詩巻」、詩では「赤壁賦」という不朽の名作を生み出しています。政治的挫折を書制作のエネルギーにかえて表現ができる、まさに「書は人なり」を体現したような人物です。書においては王羲之をはじめとして、顔真卿や李?、楊凝式などを学んで大成しました。特に、行書作品で最大の実力を発揮したという評価を受けています。今回は「黄州寒食詩巻」、「帰去来辞」、「羅池廟碑」の拓本を紹介しています。黄庭堅は、蘇軾のもとで詩文を学び、お互いの書の批評のやりとりもするなど、蘇軾とは師弟関係にありつつも、同時に友人でもありました。政治家としては、蘇軾と同じ旧法党支持の立場をとったために左遷されるなど、同様に不遇な生涯でした。書は顔真卿や懐素など、特に唐代以降の革新的な書を中心に学んだとされます。横画に独特のリズムを持たせ、縦画を針のように尖らせて抜き放ち、左右のハライを強調してダイナミックな字形にするなど、変化の妙を尽くした名品を残しています。特に、行書や草書にその特徴がよくあらわれています。今回は「松風閣詩巻」の拓本を展示しました。宋の士大夫(エリート官僚)社会にあって、米?は、科挙の試験に合格しておらず、進士ではありませんでしたが、書画家、そして収集家としては抜群の知名度を誇っていました。その並外れた審美眼をもって、北宋の徽宗皇帝が創設した書学博士の任を受け、宮廷所蔵の書画鑑定にあたるという天職に恵まれ、生涯、書画に没頭した人生を送りました。書は王羲之、?遂良など、晋から唐時代の名家の書を学び、特に行書、草書に多くの傑作を残しています。その画もまた、後世に多大な影響を与えました。北宋の四大家の中で、最も顕著に王羲之の書法を受け継いでいることからも、現存する多くの作品が手本として広く学ばれています。今回は「蜀素帖」の拓本と、大変珍しい「山水図軸」を紹介しています。
台東区立書道博物館研究員 鍋島稲子(なべしま・とうこ)
![]()
 書道博物館と中村不折コレクションについて(十二)
書道博物館と中村不折コレクションについて(十二)
平成20年8,9月号
今年は良寛(1758~1831)の生誕250年にあたり、良寛に関する特集記事や展示などが行われているようです。当館でもその流れに乗ることにし、夏休み企画として良寛関連の展示を行なうことにしました。今回は、中村不折コレクションのなかから良寛の作品、および良寛と同時代に生きた亀田鵬斎、小林一茶の作品を公開すると同時に、良寛がお手本として学んだとされる懐素(725~785)を中心とした書の古典を紹介し、良寛書の原点を探るというものです。また、良寛の書に特別な思いを寄せていた中村不折の作品もあわせて展示します。不折は良寛の書を蒐集(しゅうしゅう)し、それをもとにさまざまな随筆を書いています。中には、良寛の書が絶大な称賛をもって迎えられていることに疑問を投げかけている内容もありますが、不折が良寛の書に畏敬の念を抱いていたこともまた事実です。不折の行書や草書作品には、あるいは良寛の書からヒントを得たのではと思われるものも少なからずあります。今回の展示で、良寛から不折まで、時代を超えて受け継がれてきた“良寛の趣”を感じとっていただければ幸いです。最後に、不折の良寛に関するエッセイを抜粋してご紹介しましょう。良寛という人物を、平易な言葉で率直に語っています。「良寛の書の面白味といふ点は、俗気といふものが微塵もないことと、いかにも飄逸(ひょういつ)な点とである。これは良寛の天稟(てんぴん)、その人格から由来したもので、彼の人格はあくまでも純粋であり高潔であつた。そして、彼は特に書を能くしたばかりでなく、詩も作れば歌も詠む。また時には俳句もやるといふ、まことに多能多芸な坊さんである。否、坊さんといふよりも、一種の芸術家として見た方が、むしろ当つているのかもしれぬ。と、いふやうなことさへ考へらるる。その書は主として懐素(かいそ)を習つたらしい。殊に『自叙帖(じじょじょう)』と『千字文(せんじもん)』とは専ら学んだやうに思はれる。それに字数は極めてすくないものであるが、西安府にある『律公帖(りつこうじょう)』や『蔵真帖(ぞうしんじょう)』をも一通り研究したもののやうに解せられる。仮名は小野道風の『秋萩帖(あきはぎじょう)』を手本にしたといふ説もあるが、あるいはそれが事実なのかもしれない。」(中村不折「僧良寛の書に就いて」『書画骨董雑誌』第34号・昭和12年5月より部分抜粋したものです)
台東区立書道博物館研究員 鍋島稲子(なべしま・とうこ)
![]()
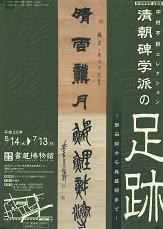 書道博物館と中村不折コレクションについて(十一)
書道博物館と中村不折コレクションについて(十一)
平成20年6,7月号
3月中旬に、『日中書法の伝承』という展覧会が東京美術倶楽部において開催されました。この展覧会では、東京国立博物館と書道博物館がアドバイザーとして協力し、展示や図録制作などにも携わりました。その際に、私が担当した分野が碑学派でしたので、このネタをこの展示のみで終わらせるのは大変惜しいと考え、是非自分の博物館展示にも生かしたいと思い、今回の展示を企画した次第です。碑学派台頭の嚆矢となった金農や鄭燮を筆頭に、碑学派の祖である鄧石如から清朝末期の呉昌碩までの作品や題簽・題跋、彼らの原典となった拓本などを中村不折コレクションのなかから紹介しています。中村不折コレクションは、清朝碑学派の作品そのものよりも、碑学派が学んだ拓本やそれらに書かれた跋文など、彼らの学問的背景となった資料が充実していることが特徴です。
では、清朝碑学派について概観してみましょう。清朝は、それ以前まで漢民族支配であった明朝に代わって満州族が実権をにぎり、3世紀の長きにわたって続いた中国史上最大規模の領地統轄を誇る国家です。国民の大半を占める漢民族の反感を招かぬよう最初に掲げたことは、漢民族の伝統文化を尊重し、それらを積極的に吸収することでした。皇帝たちによる古典編纂の文化事業奨励などは漢民族に対する懐柔策の一環でしたが、こうした活動が、古典籍の考証そのものを学問の目的とした考証学を促進させる結果を生みました。清朝中期頃より考証学が盛んになり、その影響を受けて金石学がひときわ活発化しました。この実証的な精神は書学にも反映し、多くの学者や書家たちの関心を、金石資料に向けさせることとなります。彼らははじめ唐時代の石碑や漢時代の隷書に注目していましたが、やがて山野に埋もれた石碑や青銅器にも視野を広げ、野趣あふれる北碑(北魏時代を中心とした北朝の石碑)の美しさに魅了されます。
こうした風潮が広く浸透し、金石資料に書表現の拠りどころを求めた「碑学派」とよばれる一派が台頭します。碑学派の祖といわれる鄧石如は、篆書や隷書において卓越した手腕を発揮し、幾世紀にもわたって信奉されてきた王羲之を主とする法帖中心の学書方法に新風を送り込みました。その後、阮元や包世臣らが、金石資料に関する知識と見解をもとに北碑唱導説を打ち出したことで、碑学研究は世の趨勢を占め、碑学派は清朝書学の主流となります。
清朝後期になると、呉大澂、呉昌碩たちが活躍します。彼らは、金文や石鼓文などの要素をとり込んだ書風を得意としました。北碑一辺倒の傾向から、さらに時代を遡った殷、周、秦時代の資料にまで広がり、書の表現は多様化していったのです
台東区立書道博物館研究員 鍋島稲子(なべしま・とうこ)
![]()
書道博物館と中村不折コレクションについて(十)
平成20年4,5月号
書道博物館では、他館との連携をはかり、展覧会を催すことがあります。現在「蘭亭序」と題し、流觴曲水の宴の時期にあわせて、東京国立博物館東洋館と同時期に蘭亭序及びその関連資料を公開しています。
所蔵品の移動は、物に対して大変な負担がかかり、劣化させる一因にもなります。そこで考えたのが、物を移動させるのではなく、人が動くことでより多くの作品に親しんでもらうという方法です。しかし、これは連携する相手の博物館に匹敵するような収蔵品内容でなくては成立しない企画です。今回の連携が実現できたのも、やはり不折コレクションが大変質の高い優品だったからだと思います。ちなみに、今回二館で展示されている作品は、昭和四八年に開催された「昭和蘭亭記念展」(王羲之が蘭亭の雅会を行なった年から数えて28回目の癸丑の年に行なわれた)において出品されたものが中心となっており、蘭亭記念展の再来ともいうべき豪華な内容です。
東晋時代・永和九年(353・癸丑)暮春の初め、王羲之は会稽山陰(浙江省紹興)の蘭亭に名士を招いて詩会を催しました。せせらぎに浮かべた杯が流れ着く前に詩を賦し、詩が出来なければ罰として酒を飲むという、文人ならではの雅宴です。その日、二篇の詩を成した者11人、一篇の詩を成した者15人、詩を成せず罰杯として酒を飲まされた者は16人でした。王羲之はその詩会で成った詩集の序文を揮毫しました。これが、王羲之の最高傑作と賞賛される蘭亭序です。
王羲之の書をこよなく愛した唐の太宗皇帝は、家臣の蕭翼に命じて、僧・弁才のもとから苦心惨憺の末に蘭亭序を入手しました。能書の臣下に蘭亭序の臨書を命じると、欧陽詢の臨書が迫真の出来ばえでした。そこで欧陽詢の臨本を石に刻し、その拓本を皇子、王孫、功臣に特賜しました。しかし、太宗は崩御に際して蘭亭序を殉葬させたため、蘭亭序の原本は伝存しません。
南宋時代、蘭亭序の収集は過熱し、士大夫は家ごとに蘭亭序を石に刻したと言われます。拓本を元に新たな拓本が作られ、実にさまざまな蘭亭序の拓本が現れるようになりました。王羲之傑作の残影が後世に与えた影響はまことに計り知れなく、蘭亭信仰とでも言うべき状況の中で、歴代の文人は善本を求め、自らの理想とする蘭亭序像を思い描いてきたのです。
王羲之会心の作といわれる「蘭亭序」の世界を存分にお楽しみください。
台東区立書道博物館研究員 鍋島稲子(なべしま・とうこ
![]()
書道博物館と中村不折コレクションについて(九)
平成19年12月、20年1月号
書道博物館では、毎年この時期にリクエスト展示を行なっています。館内設置の「展示希望ノート」に書かれた作品で、近年展示していないものを中心に紹介するという企画です。今回は、その中から明治書道史を傍証する資料ともいえる珍しい拓本を紹介しましょう。中村不折コレクションには「爨宝子碑」(東晋/義熙元年・405)の拓本が数冊あります。拓本名品展のような場合は、その中でも文字の摩滅が少ない最旧拓が展示され、他の爨宝子碑はなかなか陽の目を見る機会に恵まれません。そこで今回は、いつもと違った視点で紹介しようと、これまで展示したことのない爨宝子碑を陳列することにしました。それは、楊守敬が日本に携えてきたという自身の跋文と、楊守敬から副島種臣(号:蒼海)に贈られたことを示す、不折書の題簽がついた珍しいものです。楊守敬は、明治十三年に碑帖類一万点以上を携えて来日し、明治書壇に新風を吹き込んだことで知られていますが、半ば定説となっている膨大な碑帖の数にもかかわらず、楊守敬が実際に携えてきた碑帖そのものを目にする機会はほとんどありません。楊守敬と交流のあった人物としては、日下部鳴鶴・巌谷一六・松田雪柯などが知られていますが、この拓本における題簽は、楊守敬が種臣とも一定の交流を持っていたことを示唆しており、当時の日本書道界の様子をうかがうことができる大変興味深いものです。跋文において、楊守敬は「この碑は遠く雲南の南寧にあるために、拓本も大変希少で金石家の多くは所蔵していない。今これを携えて日本に来たが、これは陝西にある碑林の諸本と同様の価値を持つほど善いものである。それほど善い拓本ならば自分で用いればよいが、あなたに差し上げてしまう」と、大変貴重なものであることを記しています。楊守敬賞賛の拓本を譲り受けた種臣の喜びもまたひとしおであったにちがいありません。また、この拓本が種臣から不折へと渡ったという事実もなかなか面白いことです。この爨宝子碑は、言わば“守り本尊”として、種臣同様、不折もこよなく愛した古典でした。種臣と不折の作品に共通する「奇抜で楽しい特異な書風」は、ひょっとするとこの爨宝子碑あたりに起源を持つのかもしれません。今回は、拓本に書かれた所蔵者たちの書きつけから、明治書壇の裏舞台に思いを馳せてみました。
台東区立書道博物館研究員 鍋島稲子(なべしま・とうこ)
平成19年10,11月号
秋季特別展の時期がやってきました。多くの博物館・美術館は気候のよい10月頃に優品展を開催しますが、これは来館者が出かけやすい季節という理由のみならず、収蔵品にとっても温湿度が安定した時期であり、展示環境が良いからなのです。書道博物館では、今から約1400年~1100年前に書かれた貴重な肉筆の作品を公開します。20世紀の初頭、敦煌やトルファンの石窟から多数の古写経類が、イギリス、フランス、ロシア、日本などの中央アジア探検隊によって発掘されました。それまで石碑の拓本や法帖などを中心に編まれていた古代中国書法史に、これらの古写経類は画期的な文字資料として登場しました。その資料的価値は、①肉筆であること、②書かれた年代が明記されていることに集約できます。これら古写経の出現により、中国書法史はよりいっそう充実したものになったのです。中村不折が古写経類の蒐集をはじめたのは大正初期であり、その後亡くなるまでの三十余年間で、総数では約200件、断片を個別に数えれば優に800点は超えるほどの膨大な古写経コレクションを形成しました。蒐集した古写経類の多くは、金石考証に長じ、収蔵にも富んだ王樹?や梁素文らが新疆在任時代に現地で直接収得したものが中心です。彼らの眼識を以って蒐集したものは、世界に冠たるイギリスのスタイン・コレクション(大英図書館所蔵)、フランスのペリオ・コレクション(フランス国立図書館所蔵)などに比しても決して遜色のないものであり、質・量ともに世界的な水準を誇っています。今回は、この古写経のなかでも、隋・唐時代の、美しい楷書で書かれた写経や、珍しい草書の写経を展示いたします。また、こうした新出土資料の他に、古来より中国の皇帝たちに愛されてきた伝世品としての肉筆作品があります。その最も著名なものとして知られる、唐時代を代表する能書家であり、初唐の四大家としても名高い顔真卿が書いた世界唯一の肉筆楷書作品『自書告身帖』(唐・建中元年・780年)を特別公開します。また、唐時代に臨摸された『月儀帖』、王献之の『地黄湯帖』など、中村不折コレクションのなかから選りすぐった名品の数々を紹介いたします。隋・唐時代に書かれた、美しい肉筆作品の魅力をたっぷりとご堪能ください。
台東区立書道博物館研究員 鍋島稲子(なべしま・とうこ)
![]()
書道博物館と中村不折コレクションについて(七)
平成19年8,9月号
昨年のちょうど今頃、当館では中村不折・生誕140周年記念展として『不折と子規・鴎外・漱石』という、不折が生きた明治時代を特集した展覧会を開催しました。この時にタイトルとなった不折以外の三人は、小学校の教科書にも出てくるようないわば超有名人ですが、不折を知る人は書画の世界に接点がない限りほとんどいないのが現実です。そこで、不折の知名度を上げるには、当館で定期的に不折を特集する必要があると考え、今年の夏は“中村不折をもっと身近に”と、私たちの生活の中で見ることができる不折の書を紹介することにしました。もちろんそれが展示のメインではありませんが、不折に親しみを持ってもらうための一手段として、そうしたコーナーを設けました。例えば、みなさんよくご存知の新宿「中村屋」の看板文字、あれは不折の揮毫です。この文字は、包装紙をはじめ中村屋商品のあらゆるものに使用されていますから、コンビニのレトルトカレー売り場でも不折の字が並んでいることになります。三田の慶応大学正門前にある和菓子の「大坂家」、不折揮毫の木額がまさに店の看板としての役目を果たすべく、屋根瓦の上に堂々と掲げられています。店内のイチオシ商品“秋色最中”の文字も不折が書いています。小田原駅近くの松坂屋という和菓子の看板「松坂屋」も不折揮毫のもので、店内にその木額があります。大阪屋さんも、ロゴはすべて不折の書を用いていますので、レシートの店名部分にも不折の文字がもれなくついてきます。それから、日本酒を飲む方はおそらく目にしたことがあると思いますが、「真澄」というお酒のラベルも不折が書いています。また、真澄と同じ会社で製造している「信州一味噌」の文字も不折です。スーパーのお味噌コーナーで見ることができます。書道博物館と同じ台東区内にある浅草の浅草寺裏手には、九代目市川団十郎の像がありますが、その台座には、森?外が撰文し中村不折が書した銘文が刻されています。こんなふうに、みなさんの近くで不折の字は意外と活躍しているのです。現在開催中の『明治ニッポンの書―不折作品を中心として―』は、子規・?外・漱石の手紙のみならず、伊藤左千夫や与謝野鉄幹による美しい筆致で書かれた手紙も展示しています。また、日下部鳴鶴の手紙や河井?廬の印など、明治書道界の重鎮であった人たちが、不折との交流のなかで生まれた作品もあります。そして“不折流”といわれた独特の書きぶりが顕著な明治期以降の不折作品も展示しています。しかし、そうしたものだけではやはり不折はみなさんにとって遠いままかも知れません。今回の企画では「生活の中に息づいた不折の書」という切り口で、みなさんと不折との距離がグッと縮むような機会もつくってみました。
台東区立書道博物館研究員・鍋島稲子(なべしま・とうこ)
![]()
書道博物館と中村不折コレクションについて(六)
平成19年6.7月号
「拓本の世界―三館所蔵善本碑帖展―」が始まりました。東京国立博物館の高島菊次郎コレクション、三井記念美術館の三井高堅(たかかた)コレクション、そして書道博物館の中村不折コレクション、いずれも世界屈指の拓本名品を各館において公開しています。今回は、この展覧会を楽しむための“拓本鑑賞のツボ”についてお話しましょう。拓本は、書の鑑賞やお手本として古来より貴ばれてきました。世に知られる最古の拓本は唐代のものですが、石碑を拓にとること自体はそれ以前から行なわれていたようです。一般に、拓本は写しとった時代が古いものほど珍重されます。なぜなら、石碑に刻された文字は年月の経過とともに風化または損傷し、次第に原形から遠ざかってしまいますが、旧拓を見れば摩滅してしまった文字についても鮮明な字画を確認することができるからです。石碑そのものが失われた場合には、拓本のみがその原碑の字姿を伝えるものとなり、資料的価値もさらに高くなります。こうした石碑からの拓本のほかに、中国歴代の名筆を石や木に刻して拓をとったものもあります。かつて、数少ない真筆の名品はごく限られた人々にのみ収蔵が許されていました。そうした稀少な作品を広く普及させるため、現在の印刷(いわゆるコピー)に相当するものとして拓本の技術が考案されました。王羲之などは、書聖といわれながらも実は真筆が残っておらず、こうした拓本によってその書を鑑賞することができるのです。さらに時代を経るにしたがって、今度は拓本をとることそのものを目的として名筆を木や石に刻し、編集するようになりました。これを「法帖」と言います。ところで、名品といわれる拓本には、ほぼ必ずといっていいほど多くの印が捺されています。これは、拓本の旧蔵者や鑑賞者が捺した、自らの名を示す印であり、世に伝わる名品を所蔵、あるいは鑑賞した証を後世に残すために捺されたものです。時の政治家や学者、書家、皇族などのものが多く見られます。印のほかに、款記や考証、おぼえなどを記した跋が、拓本の帖首や帖末などの余白に書き込まれることも少なくありません。跋文から、拓本の由来や旧蔵者などがわかることもあります。こうした著名な人物の印や跋があることで、拓本の理解も深まり、その価値もまた一段と高まるのです。書の手本として拓本の印刷物を見ることの多い昨今ですが、拓調の微妙な味わいや、立体感あふれる線質の切れ味を観察するには、やはり拓本の実物を見るに限ります。古典の真の姿を「拓本」でじっくりと鑑賞して下さい。そして“かっこいいな”と思う書に出会え、その技術を自身の作品制作に生かすことができたら、書のおけいこもまた一段と楽しくなるにちがいありません。
台東区立書道博物館研究員・鍋島稲子(なべしま・とうこ)
![]()
書道博物館と中村不折コレクションについて(五)
平成19年4,5月 7号
今回は、現在書道博物館で開催中の企画展『中村不折コレクション名家による尺牘(せきとく)と臨書作品』の展示から、注目の作品を紹介してみましょう。展示テーマにある「尺牘」とは、手紙のことです。「牘」の字は、もともと木や竹の札を指し、これが転じて文字を書き付けた文章のことを示しています。中国では手紙類を一尺の木や紙に書いていたことから「尺牘」と呼ぶようになりました。今回展示の中で最も古いものが、唐時代・如意元年(692年)頃に書かれた尺牘です。この尺牘は、華厳宗の大成者である名僧・賢首(けんしゅ)国師(こくし)(諱(いみな)は法蔵(ほうぞう))が、唐の西京から、遠く新羅にいる義湘(ぎしょう)法師(ほうし)に宛てて送ったものです。義湘もまた、朝鮮において華厳宗を確立した高僧として知られ、若頃は法蔵とともに長安の終南山の至相寺で、華厳教学の創始者・智儼(ちごん)に師事した人物です。尺牘の字形はやや縦長で、穂先のきいたきりりと清々しい行書で書かれています。本文に続き、陳廷言や銭宰、王?、楊守敬など元~清代まで計八名の跋文が書き込まれ、安岐や王懿栄といった清朝の学者たちの印も捺されています。中村不折は、昭和3年12月にこの尺牘を入手しました。当時、中国文物を扱う江藤長安荘の展観で出品されていたもので、不折が江藤と交渉している現場を、西川寧が目撃していたというエピソードもあります。賢首国師の書は、この尺牘以外に伝わっていませんが、同一文のものが天理図書館に所蔵されています。尺牘は、書き手の気負わない日常平生の姿をうつし出しています。この作品もまた、賢首国師の息づかいをうかがうことができる貴重な資料といえるでしょう。
台東区立書道博物館研究員 鍋島稲子(なべしま・とうこ)
![]()
書道博物館と中村不折コレクションについて(四)
平成19年2,3月号
こうして、様々なルートで手に入れたコレクションは、いつのまにか一万点を優に越える膨大なコレクションにまで発展していきました。ここにいたって問題となったのが、それらの貴重な収蔵品を、劣化を防ぎつついかして次世代へと継承させていくかということです。その結論はまず、大正十四年に拓本や紙本墨書類の収蔵可能な書庫の建設というかたちで実を結び、さらに昭和八年には「金石館」と命名した金石資料の陳列施設が建造され、保存と同時に公開もできるような配慮がなされました。その後、手狭となったこの金石館が増築され、昭和十一年、財団法人「書道博物館」が正式に発足する運びとなったのです。この博物館建設は、書道界のみならず、美術界全体での関心事でもあったようで、幾度となく新聞記事となり、その進捗状況が伝えられました。昭和八年七月十一日付の報知新聞「中村不折画伯が蒐集品を挙げて書道博物館へ」に始まり、東京毎日新聞、日本新聞、東京朝日新聞、都新聞、伊那毎日新聞などが博物館建設についての記事を載せています。開館前の昭和十一年には東京朝日新聞が「不折画伯の宿願書道博物館出来上る 菊よ薫れ・此苦心四十年汗の蒐集」と題して大々的に報じました。また、書道界の新聞である書壇新報では、「書道博物館竣成祝賀会 各派代表一堂に集り 書道界未曾有の大偉観」として祝賀会の様子を記事にしています。そのコラムを読むと、祝賀会の発起人代表であった河井セン廬が、書道博物館の開館を心から喜んでいたことがよくわかります。コラムの内容を以下に紹介しましょう。「12月16日、ステーションホテルに於ける書道博物館竣成祝賀会は、書道界各派の有力者百余名を網羅したといふ書道界たち初まつて以来の豪華版であったが、中にも、河井セン廬翁が立つてものを言ふということは、書道界珍中の大珍事で、恐らくさうはいふものの当日になつてきつと立つまい、との見解が各所で行はれてゐたものである。ところが、開会の辞がすんで、発起人代表の挨拶となると、すつくと立ち上つたセン廬老、朗々と祝辞を読み上げて満場の拍手を浴び、莞爾と笑つて一輯、ここに所謂珍中の大珍事が完全に成立したわけである。あとになつて、川村驥山老、君ィ、涙が出たよ、といつた」セン廬と不折との親交の深さがうかがえる、心温まる話です。
台東区立書道博物館研究員 鍋島稲子(なべしま・とうこ)
![]()
書道博物館と中村不折コレクションについて(三)
平成18年12月、19年1月号
不折が手に入れたコレクションは、「自書告身帖」のように大変高価な美術品もあれば、掘り出し物もありました。年の暮れのしかも大晦日、不折が神田の町をひやかし半分で歩いていると、後漢時代の石碑「孔宙碑」(延熹7年・164)の拓本が十円で売られていました。不折はそこでさらに九円に負けさせて買い、家に帰って調べてみると、なんとそれは時価一万円程の北宋拓の優品だったそうです。拓本の帖末には、明の嘉靖28年(1549)に書かれた孫楨の跋文も添えられています。この「孔宙碑」を、不折の友人で拓本などの目利きでもあった河井?廬に見せたところ、?廬自身も「今までいろいろのものを手に入れたけれども、これほどのものは一冊もあるまい」と言ったそうです。このような北宋拓など、中国へ行ってもなかなか見つからないものが、ごく身近な神田の夜店で手に入ったわけで、不折が購入した拓本の中では一番の掘り出し物といえるでしょう。こうしたものの他に、交換という手段で手に入れたものもあります。 大正11年頃、不折は当時駐日公使であった胡維徳の所蔵する数多くの拓本を鑑賞する機会に恵まれます。そこで後漢時代の「開通褒斜道刻石」(永平9年・66)の旧拓本を目睹するのですが、その迫力に不折は「一見実に卒倒しさうに感じた」と後述しています。晩餐の席で不折は、胡維徳に「開通褒斜道刻石」の拓本を譲ってほしいと迫ります。はじめ胡維徳はただ笑って相手にしなかったそうですが、なおも根気強く懇願しつづける不折の熱意に絆され、不折作の絵画作品と交換する約束をして、不折に拓本を譲ったといいます。
台東区立書道博物館研究員 鍋島稲子(なべしま・とうこ)
![]()
平成18年10,11月号
中村不折は、日清戦争従軍記者として中国へ渡った明治28年から蒐集をはじめ、亡くなる昭和18年までほとんど毎年購入していました。中村家が購入時の領収書やメモを残していることより、取得年代や価格、仲介者等が判明するものもあり、その一端からコレクション形成過程を垣間見ることができます。例えば不折コレクションの中で最も有名な唐の顔真卿「自書告身帖」(建中元年・780)、これはかつて宋時代に皇帝のコレクションとして内府に所蔵されていたものでした。その後、民間に渡り、韓●冑(115~1207)、賈似道(1213~1275)らが所蔵し、明時代に徐守和(17世紀)、清時代では梁清標(1620~1691)、安岐(1683~?)の収蔵となった後、乾隆帝の時に再び清朝内府に入りました。清朝末期には恭親王、そして道光帝の曽孫にあたる溥儒(1896~1963)の所蔵となりましたが、この時代、復辟運動が盛んに行われ、皇族は資金作りのために数多くの収蔵品を手放しました。なかには日本へ渡ってきたものもあり、その一つに「自書告身帖」があったのです。最初は三菱などの財閥に話がいきましたが、値段の折り合いがつかず、回り回って不折のところに話がきました。そして何度も交渉を重ねた末、不折は昭和5年7月30日に3万円で入手しました。この頃は家が700円で買えた時代です。当時としてはあまりの高値に、不折は分割で支払うことにし、残額は絵画の収入を当てていくことにしたそうです。こうして天下の顔真卿「自書告身帖」は不折の有に帰し、書道博物館の名品として世に知られることとなったのです。
台東区立書道博物館研究員 鍋島稲子(なべしま・とうこ)
![]()
平成18年8,9月号
書道博物館は、洋画家であり書家でもあった中村不折(1866-1943)が四十年あまりにわたり独力で蒐集した、中国及び日本の書道史研究上重要なコレクションを有する専門博物館です。中村不折コレクションの総数は、およそ一万数千点あります。その内容は甲骨文や青銅器、仏像などの金石関係から、敦煌文書や中国歴代書家の真蹟本、碑版法帖などの紙本墨書関係にいたるまで実に幅広いものです。ですから一見つながりなく蒐集したかのように思えますが、これらはすべて「文字研究資料」いう観点から蒐集したもので、収蔵品の大半に「文字」が施されていることがコレクションの特徴です。漢字の始まりである甲骨文から、今日我々が使用している楷書までの文字変遷が、中国の文物によって辿ることができるのです。この膨大な数のコレクション蒐集は、明治二八年に不折が正岡子規(1867-1902)とともに日清戦争従軍記者として中国に渡り、文物に触れる機会を得たことに始まります。その時には拓本を数点持ち帰るにとどまりましたが、その後、東京本郷湯島の文求堂をはじめ琳瑯閣、文雅堂、晩翠軒などといった、中国からの書籍や拓本類を輸入していた書店に足を運び、気に入ったものがあれば購入しました。やがて不折が文物を蒐集していることが知れてくると、中国往来の商人たちが不折のところへ持ち込んでくることも多くなり、あるいは欲しいものがあれば中国へ使いの者を送ってまで購入することもあったそうです。次回からは、コレクションの形成過程を交えながら、書道博物館の名品を紹介していきたいと思います。
台東区立書道博物館研究員 鍋島稲子(なべしま・とうこ)
![]()
鍋 島 稲 子 さ ん と の 出 会 い 苅田 銅山
2008年2,3月10号
今号では、「精錬」創刊以来、『書道博物館と中村不折コレクションについて』というタイトルで、毎号価値ある連載文を戴いている 鍋島稲子(なべしま とうこ)さんを改めて紹介したいと思います。
私、銅山は以前、游墨会という書論研究グループに所属していた時代がありました。今からおよそ、15年も前のことです。約20名弱の会員で組織され、メンバーは関東各地の書道教室の先生方で、とても意気が合い、仲の良い小集団でした。近代書道を深く理解するため月一度、室内で勉強を重ねたり、または半年に一度位のペースで、そのときの研究課題にまつわる彼地を訪ね、更に興味を深めていく学習方法でした。当時は、毎会の開催日が待ち遠しいくらい、それはそれは楽しい集いの会でした。
或年の研究課題が「中林梧竹の書」を追求することになりました。回を重ねる毎に、深奥で神秘さ漂う梧竹の書の世界に、一同すっかり参り、その魅力に引き込まれる一方でした。とうとう、いても立ってもいられず、梧竹の生誕地、佐賀県は小城の里を訪ねようということになったのです。勢いとは怖いもので、図々しくも梧竹のお孫さんの中林秀利さんに接触を計る始末でした。そして、ついには二泊三日の旅程の間、なんとその中林秀利さんのご案内で、地元在住の梧竹作品はじめ、明治書家の肉筆を沢山所蔵している素封家に引き合わせてくれたり、梧竹由縁の寺社や、小城の梧竹記念館まで巡ることができました。まるで夢のような贅沢極まる三日間でした。その上、ラッキーだったのは、宿泊していた曙旅館にて、中林秀利さんのご仲介で、たまたま当地を訪れていた全国梧竹の会の会長、日野俊顕先生や東京梧竹の会、会長の本野克彦さんに引き合わせて戴き、梧竹について書法やエピソードなど、さまざまなお話を深夜に及ぶまで伺うことができたというおまけつきです。その歓談中に、今、東京で梧竹研究に没頭している才媛、鍋島稲子さんのことを初めて教えていただいたのが、そもそも鍋島稲子さんを知り得るきっかけだったのです。
やがて、二度と味わえないような楽しい旅を終えた、私達の次のターゲットは、その鍋島稲子さんをわが游墨会にお迎えし、講義を聴くことに全員の意見は一致したのでした。暫くして、游墨会の例会の輪に念願の鍋島稲子さんも加わっていただき、梧竹のさまざまなお話をしていただくことも実現したのです。その時、私達一同は難しい学者先生の講義かなと予想していたのですが、笑いも混じえて、とても和やかでほのぼのとしたひとときが、流れたように回想します。ところで、その鍋島稲子さんという方は世が世だったら、お目通りも叶わない小城鍋島藩正統のお姫様だったのです。なんと小城鍋島家九代直堯の血筋ということです。手元に平成9年4月5日付けの佐賀新聞の記事がありますので少々のぞいてみます。鍋島稲子さんは1965年名古屋市生まれ、筑波大学芸術専門学群博士課程修了と記載されています。なんと日本で初の芸術学博士だったのです。長年に亘り、梧竹研究に取り組まれ、博士論文も「明治書道の展開と中林梧竹―北派の書の移入をめぐって」ということで、現代の梧竹研究の第一人者であると紹介されています。鍋島稲子さん自身も「客観的に、冷静に、梧竹だけに照準をあてるのではなく、他の同時代の書家達と比較しながら本格的に梧竹を追求したい。」と、梧竹研究がライフワークであることを述べられています。小1の頃から小城の祖母に勧められて始めた書道、得意書体は楷書。書家としても公募展などで活躍中と記事は続いています。
現在は財団法人・東京都台東区立書道博物館で研究員として、近代書道史における功績者の一人、中村不折の研究に、まさに精力的に腐心されている現況とのことです。
今、思い起こせば、ちょっとしたご縁でお知り合いいただき、銅山からの厄介な原稿依頼にも爽やかに快諾して戴いたところにも鍋島稲子さんの恬淡とした融和的なお人柄を感ぜずにはいられません。
鍋島稲子さんにおかれましては益々、ご活躍を願うばかりですが、そのご多忙の中でも、なんとか時間を割いて引き続きわが小誌にも筆を寄せていただけたらと渇望する次第です。